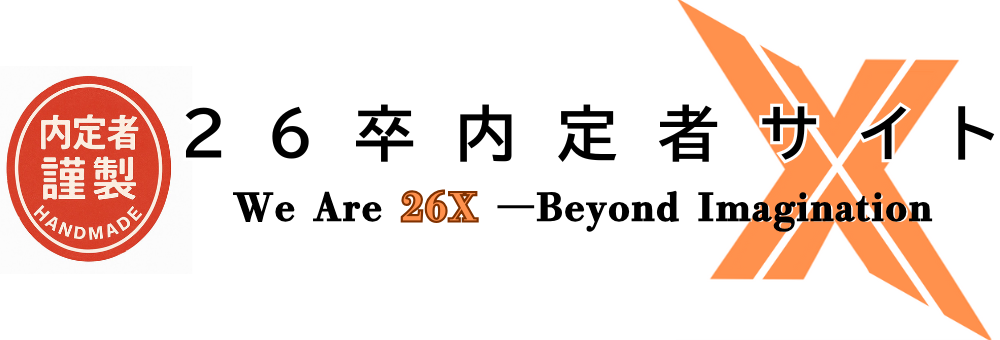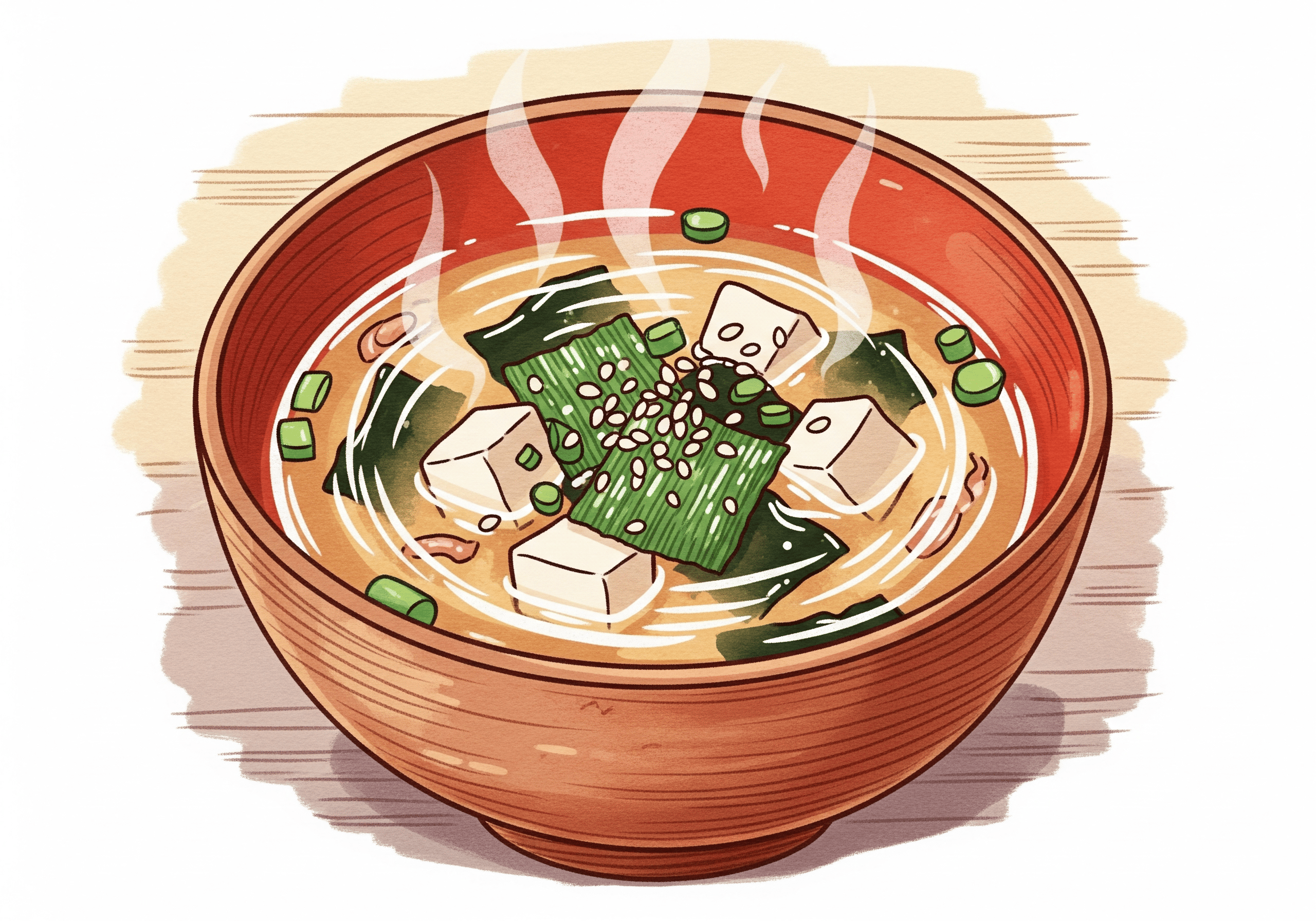毎日、仕事や勉強に追われていると、どうしても目の前のことに集中しがちになりますよね。
新しい知識を吸収したり、スキルを磨いたりすることはもちろん大事ですが
たまにはふと立ち止まって、普段の生活では得られない
「新しい何か」に目を向けてみるのはいかがでしょうか?
先日、ふと日本の伝統的な食文化に興味が湧き、そこから毎日飲む味噌汁への関心が深まりました。
その背景にある文化や、実際にどう作られているのかを知りたいという思いから、
長野県大町市で「味噌づくり」体験をしてきました!
スーパーに行けばさまざまな味噌が並んでいますが、
なぜあんなにも色や味が違うのか、考えたり調べたりしたことはありますか?
私自身も、今回の体験するまでは
「なんとなく大豆から作られるもの」程度の知識・認識でした。
今回体験したのは、昔ながらの製法でした。
煮た大豆を潰し、そこに米麹と塩を混ぜ合わせます。
さらに既に発酵した種味噌を混ぜ込むことで
新しい味噌の発酵を促していきます。

目の前で材料が混ざり合い、味噌の原形ができていく様子は
「作る」よりは「育てる」という感覚に近いものでした。
実際は混ぜ合わせて完成ではなく、持ち帰って家で数か月程度保管し、
発酵させてから頃合いを見て使用します。


そんな味噌ですが、最近では食卓から味噌汁が消えつつあるというお話を聞きました。
現代の忙しい生活や食生活の多様化が背景にあるとのことでしたが、
やはり温かい味噌汁を飲むとホッと落ち着けますよね。
私は今回の味噌づくり体験を通して、
教科書やインターネットからは得られない、五感で感じる新た発見があり、
普段触れることない文化的側面に触れることの大切さに気付けました✨
今回のブログは、これまでと少し趣向を変えて、
内定者のプライベートでのイベントについて紹介しました!
内定者研修のような会社関連のトピックに限らず、
このような肩の力を抜いたような内容も更新されていきますので、
次回以降もぜひチェックしてくださいね👀
それでは、また次回のブログでお会いしましょう👋